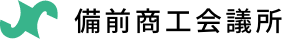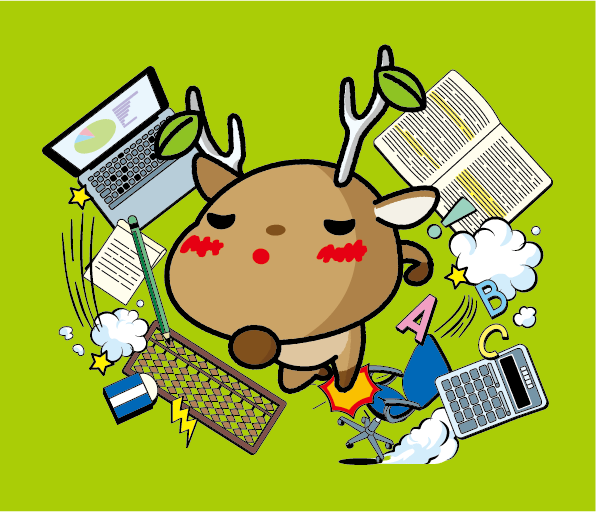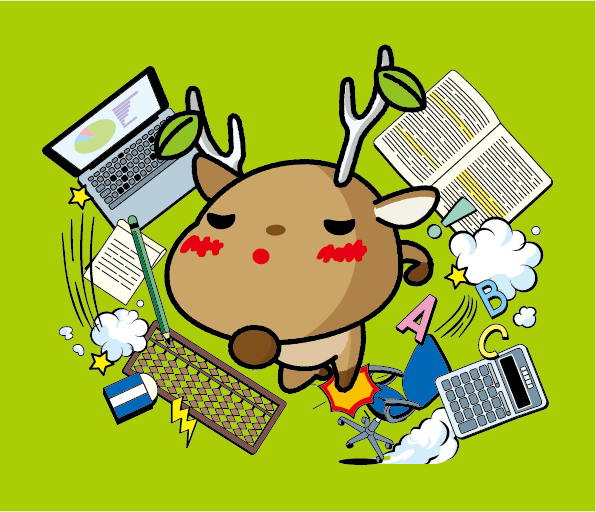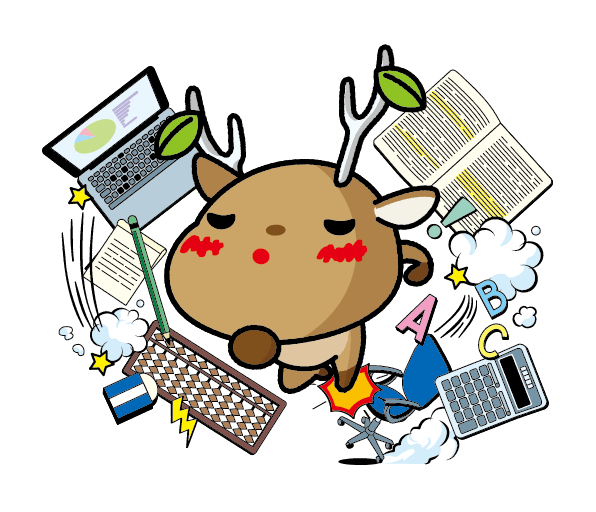簿記検定
第172回 簿記検定試験申込開始についてのご案内
2月22日(日)開催の第172回簿記検定試験の申込を開始しております。
申込期間は下記の通りです。
◆申込期間:1月6日(火)~1月23日(金)
こちらのページより申込のお手続きをお願いいたします。(*申込はインターネットのみ*)
なお、日本商工会議所では、日商簿記検定試験2級・3級について、年3回の統一試験日におけるペーパー試験に加えて随時受験可能なネット試験を開始しています。
2026年1月6日
第171回 簿記検定試験 11月16日(日)実施分 合格発表
11月16日(日)実施いたしました第171回簿記検定試験(2・3級)の合格者をお知らせいたします。
こちら のページよりご確認下さい。
〇 WEB成績照会サービス
試験種別、受験番号、生年月日、照会番号を入力により成績がわかります。
こちら のページよりご確認下さい。
〇合格証書の交付期間は12月22日(月)から概ね1ヶ月となります。
受験表をご持参の上、当所へお越しください。
(1級の合格発表は1月5日(月)です)
2025年12月1日
第171回 簿記検定試験申込開始についてのご案内
11月16日(日)開催の第171回簿記検定試験の申込を開始しております。
申込期間は下記の通りです。
◆申込期間:9月29日(月)~10月17日(金)
こちらのページより申込のお手続きをお願いいたします。(*申込はインターネットのみ*)
※試験会場の都合上、受験者人数を先着順として制限させて頂きます。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、日本商工会議所では、日商簿記検定試験2級・3級について、年3回の統一試験日におけるペーパー試験に加えて随時受験可能なネット試験を開始いたします。
2025年9月29日
令和7年度日商簿記3級合格を目指す簿記講習会を実施します!
当所にて例年実施しております『日商簿記3級合格を目指す簿記講習会』ですが、令和7年度につきましても実施いたします。
本講習会は簿記(経理事務や財務諸表を読む力、基礎的な経理管理のために必要なスキル)について、全く初心者の方を主な対象として、実務で活かせる基礎知識の習得から検定試験(日商簿記3級)対策までを行います。
近年、検定内容が徐々に難しくなっています。検定試験合格には知識の習得はもちろん、変化していく検定問題になれる必要があります。
そんな検定試験合格に向けて勉強したい方にもおすすめとなっています。
教材はネット試験対応のものを使用しています。
◆日程
9月30日(火)~11月7日(金) ※対象期間中の毎週火曜日・金曜日 全12回
(9月30日、10月3日・7日・10日・14日・17日・21日・24日・28日・31日、11月4日・7日)
◆場所
備前商工会館 (備前市東片上230)
◆講師
森末英敬 氏 (税理士)
◆定員
20名(先着順)
◆受講料
10,000円(テキスト代等含む) 初回にご持参ください。※返金不可
◆その他
日商簿記検定試験は11月16日(日) 申込受付期間は9月29日(月)~10月17日(金)です。
◆主催/後援
備前商工会議所・(公社)瀬戸法人会/東備青色申告会・和気地区雇用開発協会
◆申込先等
9月5日(金)までにチラシに必要事項記載の上FAXまたはメールをしていただくか、電話や専用フォームでのお申込ができます。
◆問合せ先
備前商工会議所
〒705-0022
備前市東片上230
電話:0869-64-2885 FAX:0869-63-1200
メール:info@bizencci.or.jp
2025年6月27日
第170回 簿記検定試験(2級・3級) 合格発表は6月23日
6月8日(日)実施いたしました第170回簿記検定試験(2・3級)の合格者をお知らせいたします。
こちら のページよりご確認下さい。
〇 WEB成績照会サービス
試験種別、受験番号、生年月日、照会番号を入力により成績がわかります。
こちら のページよりご確認下さい。
〇合格証書の交付期間は7月11日(月)から概ね1ヶ月となります。
受験表をご持参の上、当所へお越しください。
(1級の合格発表は7月28日(月)です)
2025年6月23日
第170回 簿記検定試験申込開始についてのご案内
6月8日(日)開催の第170回簿記検定試験の申込を開始しております。
申込期間は下記の通りです。
◆申込期間:4月21日(月)~5月9日(金)
こちらのページより申込のお手続きをお願いいたします。(*受付はインターネットのみ*)
※試験会場の都合上、受験者人数を先着順として制限させて頂きます。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、日本商工会議所では、日商簿記検定試験2級・3級について、年3回の統一試験日におけるペーパー試験に加えて随時受験可能なネット試験を開始しています。
2025年4月21日
第169回 簿記検定試験 2月23日(日)実施分 合格発表
◆第169回 簿記検定試験 2月23日実施分 合格発表は3月10日
こちら のページよりご確認下さい。
試験種別、受験番号、生年月日、照会番号を入力により成績がわかります。
こちら のページよりご確認下さい。
2025年3月10日
第168回 簿記検定試験 11月17日(日) 実施分 合格発表
◆第168回 簿記検定試験 11月17日(日)実施分 合格発表は12月2日(月)
こちら のページよりご確認下さい。
試験種別、受験番号、生年月日、照会番号を入力により成績がわかります。
こちら のページよりご確認下さい。
2024年12月2日
第168回 簿記検定試験 インターネット申込開始についてのご案内
当所では、第168回簿記検定試験が令和6年11月17日(日)に開催されます。
◆申込受付期間:令和6年9月30日(月)~10月18日(金)
インターネットによる簿記検定試験申込受付 AM0:00~ 開始いたします。
第168回簿記検定試験申込受付開始日に、こちらのページよりインターネット申込できます。
なお、日本商工会議所では、日商簿記検定試験2級・3級について、年3回の統一試験日におけるペーパー試験に加えて随時受験可能なネット試験を開始しています。
2024年9月30日
令和6年度日商簿記3級合格を目指す簿記講習会を実施します!※受付終了しました
当所にて例年実施しております『日商簿記3級合格を目指す簿記講習会』ですが、令和6年度につきましても実施いたします。
本講習会は簿記(経理事務や財務諸表を読む力、基礎的な経理管理のために必要なスキル)について、全く初心者の方を主な対象として、実務で活かせる基礎知識の習得から検定試験(日商簿記3級)対策までを行います。
近年、検定内容が徐々に難しくなっています。検定試験合格には知識の習得はもちろん、変化していく検定問題になれる必要があります。
そんな検定試験合格に向けて勉強したい方にもおすすめとなっています。
教材はネット試験対応のものを使用しています。
※昨年は多くの合格者が受講者から出ました!
◆日程
10月1日(火)~11月8日(金) ※対象期間中の毎週火曜日・金曜日 全12回
(10月1日・4日・8日・11日・15日・18日・22日・25日・29日、11月1日・5日・8日)
◆場所
備前商工会館 (備前市東片上230)
◆講師
森末英敬 氏 (税理士)
◆定員
20名(先着順)
◆受講料
10,000円(テキスト代等含む) 初回にご持参ください。※返金不可
◆その他
日商簿記検定試験は11月17日(日) 申込受付期間は9月30日(月)~18日(金)です。
◆主催/後援
備前商工会議所・(公社)瀬戸法人会/東備青色申告会・和気地区雇用開発協会
◆申込先等
9月6日(金)までにチラシに必要事項記載の上FAXまたはメールをしていただくか、電話や専用フォームでのお申込ができます。
◆問合せ先
備前商工会議所
〒705-0022
備前市東片上230
電話:0869-64-2885 FAX:0869-63-1200
メール:info@bizencci.or.jp
2024年6月18日