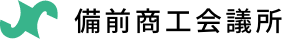備前の耐火物の歴史(第4回)
金属材料は原鉱石が異なっても製錬することによって同じ材料が得られます。一方、耐火煉瓦は原料を結合させた製品ですので、原料が異なると、それらを組合わせた全体の化学組成が同じでも製品の特性は異なります。そのため昔から、「原料を制する者は耐火物を制す」と言われてきました。備前地区ではろう石原料が産することで耐火物産業が発展してきましたが、昭和初期になると中国から、復州粘土(現在のばん土頁岩)やマグネサイトなど、日本には産しない原料が輸入されるようになり、耐火煉瓦の種類が広がりました。
昭和二年には、九州耐火が復州粘土を用いることで耐火度が高い高アルミナ質煉瓦「アルマナイト」を開発し、ボイラー等に適用しました。昭和十一年に耐火煉瓦の製造を始めた大阪窯業(現ヨータイ)でも、復州粘土を用いた高温焼成煉瓦を開発し、各所で好評を得ました。
また、四浦けい石(大分産)を用いたけい石煉瓦の需要が増加し、品川白煉瓦や九州耐火煉瓦の新工場ではコークス炉用けい石煉瓦が多量に製造されました。
原料だけでなく、昭和初期には耐火物製造設備の点でも進歩がありました。明治後期に三石で創業した深井鉄工所は大正期に入ると耐火煉瓦の製造機械の研究を始め、昭和十年には弓プレス、スクリュープレスなど、新しい成形機を実用化しました。
しかし、当時の耐火煉瓦の成形は、水分の少ない練り土を大型のプレス機を用いて高い圧力で成形する方法とは異なり、現在の5倍ほどの水分を含んだ柔らかい練り土を低い圧力で成形する方法(湿式成形)でした。写真は昭和二十七年の杵打ちランマー成形の作業風景です。 こうした湿式成形では社名の刻印や、モルタルの塗布を良くするための網目模様を煉瓦表面に刻むことも容易でした。形状的にも大型品は少なく、「並形」と呼ばれる230×114×65mmの製品が多量に製造されていました。
こうした湿式成形では社名の刻印や、モルタルの塗布を良くするための網目模様を煉瓦表面に刻むことも容易でした。形状的にも大型品は少なく、「並形」と呼ばれる230×114×65mmの製品が多量に製造されていました。
昭和十二年に日中戦争が始まり二十年に太平洋戦争が終戦するまで、耐火物の需要は高く、大正期の大戦景気の約三倍(現在の耐火煉瓦生産量と同じ程度)の生産量がありました。現在、景観用に並形サイズの使用後耐火煉瓦が敷き詰められた様子をよく見かけます。その多くは昭和前期の製品のようです。