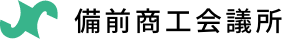備前の耐火物の歴史(第1回)
耐火物とは、鉄鋼、非鉄金属、セメント、ガラスなど約1000℃以上の1で操業する工業炉や、備前焼など各種窯業の窯で、内張りに使用されて高熱に耐えるセラミックス材料です。昔は耐火煉瓦と呼ばれていましたが、現在はコンクリートのように現地で施工する材料が多くなったため、耐火物と総称されています。備前地区には日本の耐火物メーカーの約3分の1が集まっており、世界的に見ても耐火物産業の盛んな地区の1つです。
また商業ベースでの耐火物製造が始まって127年の歴史があります。備前で耐火物が製造されてきた歴史を6回に分けてご紹介します。
日本の耐火物の製造は、幕末に大砲を鋳造するため、各地に反射炉が築造されたことから始まりました。当時の姿を残した「世界遺産」として伊豆の韮山反射炉が有名ですが、赤穂線の大多羅駅の近くにも同じような反射炉が築造されました。
大多羅反射炉は、邑久郡下阿知村の蘭方医・塩見常蔵が、岡山の宮大工棟梁・尾関滝右衛門と協力して行った民間主導の大事業でした。反射炉を1基つくるには耐火煉瓦が約2万個必要です。塩見常蔵はオランダの砲兵将校が書いた技術書の翻訳本を頼りに、大変な苦労を重ねながら、粘土を成形し、登窯で焼成して耐火煉瓦を製造しました。
慶応元年に建造された反射炉は大砲を鋳造することには成功したものの、鋼の品質が不十分であったため試射の時に砲身が破裂し、失敗に終わりました。そのため反射炉は取り壊されてしまい、現在、その跡地(旭東中学校付近)には何も残っていません。
しかし、付近を工事した時に反射炉で使用した耐火煉瓦の一部が見つかっており、西大寺文化資料館に展示されています(写真)。
このように幕末には、日本の各地で反射炉築造のため耐火煉瓦の製造が行われましたが、それらは産業として定着することなく、一時的な取り組みでした。本格的な耐火煉瓦の製造が始まるのは、明治時代となり、工部省の主導で伊豆梨本村に工場が建設されてからです。そして明治8年には西村勝三が東京に民間の耐火煉瓦会社を設立しました。
こうして明治初期の耐火物製造は関東が舞台でしたが、やがて備前地区(三石)で優れた耐火物原料が発見され、明治20年代から耐火煉瓦の産地として存在感を増していきます。